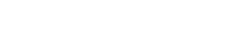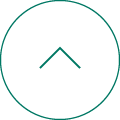MISSION
社会環境やニーズの
変化を
キャッチアップし、
時代が求める
仕組みを
開発して世に送り出す。
Atsufumi Nagata
全国本部/
仕組開発部門
全国域総合職

全国本部 開発部
生命開発グループ 兼
共同開発室 共同開発グループ
永田 敦郁
(2019年入会)
大学院で公共政策を学んでいた経験から公共性の高い事業に関心を持ち、地方部を中心とした地域の基幹産業たる農業を支えることができ、日本中を網羅したJAの事業基盤を通して自らが立ち上げた施策を全国に波及できる点に魅力を感じて入会する。
仕事相関図
普及推進部門
仕組みにかかるニーズや新しい仕組みの普及推進活動の方針について相談する。
数理部門
新しい仕組みの共済掛金率水準の算定やリスク管理について相談する。
事務・システム部門
新しい仕組みに対応したシステムや事務手続きの構築について相談する。
引受審査・支払査定部門
新しい仕組みの引受審査基準や支払査定基準について相談する。
現在の業務内容
組合員・利用者の安心につながる
仕組みを企画・設計する仕事。
JA共済連の提供する保障領域のうち、「ひと(生命保障)」分野の仕組みの開発を担っています。仕組みを開発するプロセスは大きく分けて4段階に分けられます。1つ目が、組合員・利用者の方々の保障に対するニーズをヒアリングして分析し、新しく提供する仕組みを企画すること。2つ目が、どのような場合にどの程度の共済金をお支払いするのかなど具体的な保障内容を設計すること。3つ目が、仕組みの提供にあたって契約条項をまとめた共済約款の規定作成をすること。4つ目が、開発した仕組みについて監督官庁である農林水産省から認可取得に向けた対応をすることです。この4つのプロセスを段階的に踏むことで新たな仕組みをリリースすることができます。
生命分野の保障は、年齢、家族形態などによって多様な保障ニーズが存在します。保障のラインアップの多角化や保障内容を細やかに設定できる仕組みの開発を行うことで、個々人に最適な保障提供を実現できる仕組体系を日々模索しています。
業務で心がけていること
JA共済連が果たすべき意義とは
何かを考え続けていく。
日本の農業基盤を支え、地域社会にも貢献するJA共済連ならではの特徴や要素を仕組みにどのように織り込み、差別化を図るのかという点で「発想力」が求められる難しさを感じています。一方で、共済は形のあるものではありませんが、自らのアイデアを企画としてまとめ、約款規定に落とし込み、最終的に作り上げたものが組合員・利用者の方々の生活の支えとなって数十年にわたり機能するという共済事業の根幹を担う開発ならではの面白さがあります。責任の大きさと比例して、非常にやりがいのある業務です。
入会2年目には、生命総合共済の主軸である「医療共済」の抜本的な仕組改訂に取り組みました。当時は、仕組みにかかる基礎的な知識しかありませんでしたが、先輩方の手厚いサポートのもと統計データや業界動向など外部環境の分析から、約款規定の作成、行政説明に至るまで、仕組改訂業務の一連のプロセスに携わることができたことに加え、「なぜ、組合員・利用者の方々に、今この仕組みが必要なのか」を起点として考える仕組開発の核となる視点が養われたと考えています。このような視点は、業務において論理性が問われる場面や新たな仕組み案を導き出すにあたり思案を巡らせる場面で、要として機能していると感じています。
今後の目標
農業経営を安定的に支えるための
仕組みづくりに挑戦していきたい。
医療技術の進展によって平均寿命が延伸し、「人生100年時代」と言われる長生きできる時代が訪れることが予想されます。一方で、少子高齢化に伴う社会保障の縮小、さらには新型コロナウイルスの蔓延など、生命保障を取り巻く社会環境やニーズは刻々と変化しています。そうした変化に迅速に対応するため、関連する政策動向をはじめ、経済・社会動向などの情報に対しては常にアンテナを高く張るよう努めています。また、これまでは有事の際に共済金をお支払いする仕組みが中心でしたが、開発部全体として疾病の予防など健康増進につながるサービスと一体となった仕組開発に取り組んでいます。組合員・利用者の方々の安心した生活を重層的に支えていくことのできる仕掛けの構築に向け、従来の仕組開発に囚われない広い視野を持つことを心がけています。
現在、JA共済連では、「ひと・いえ・くるま」の保障分野に加え、「農業分野の保障」を新たな事業の柱として掲げています。大きな変革期を迎えている農業において、気候変動を原因とした自然災害リスクの増加、スマート農機の利用に伴うニューリスクの発生等、営農上のリスクも多様化しています。農業の将来像を見据えながらJA共済連だからこそ提供できる仕組みを形にすることで、組合員の方々の安定した農業経営や経営発展の実現に寄与したいという入会時の想いを持ち続けながら業務に臨んでいます。
キャリア
2019 |
入会。全国本部 開発部 生命開発グループに配属。「ひと」分野の保障における仕組開発を担当する。 |
|---|---|
2022 |
共同開発室共同開発グループの業務を兼任。生命分野に加え、農業分野の保障における仕組開発にも携わる。 |
OFF TIME 休日の過ごし方

インドア・アウトドアを共に充実した
プライベートを過ごしています。
仕事終わりに観劇に出向くなど、定期的にアフターファイブを満喫しています。また、休日にはウィンドサーフィンを始めとしたアウトドアレジャーで汗を流したり、興味のある美術展に出向き刺激を得る等、インドア・アウトドア共に充実したプライベートを過ごすことで、仕事と休みのメリハリをつけるようにしています。